「受給者証」と「障がい者手帳」、どちらも障がいのある方が利用するものですが、実は目的や使い方が全く異なることをご存じでしょうか?福祉サービスを受けるために必要なのが受給者証、日常生活での割引や支援を受けるために使うのが障がい者手帳です。しかし、この違いが分かりにくく、どちらを取得すべきか迷う方も少なくありません。
この記事では、受給者証と障がい者手帳の違いを分かりやすく解説し、入手方法や手続き、具体的な使い方について詳しくご紹介します!どちらを取得すればよいか迷っている方は、ぜひ参考にしてみてください。
受給者証と障がい者手帳の違いって何?
障がいがある方やご家族の方の中には、「受給者証と障がい者手帳って何が違うの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。名前は似ていますが、それぞれ目的や使い方が異なります。
簡単にいうと、障がい者手帳は「障がいがあることを証明するもの」で、受給者証は「福祉サービスを利用するためのもの」です。では、具体的にどんな違いがあるのか、入手方法や手続きの違い、使い方について詳しく解説していきます!
受給者証と障がい者手帳の入手方法の違い
受給者証と障がい者手帳は、それぞれ申請の仕方が異なります。
受給者証の入手方法
受給者証は、福祉サービスを利用するために自治体へ申請して取得します。
- 住んでいる自治体(市区町村)の福祉課に相談する
- 申請書を提出し、サービスの必要性を確認するための調査を受ける
- 支給が決定すると、受給者証が発行される
ポイント:医師の診断書や障がい者手帳がなくても申請できる場合があります。
障がい者手帳の入手方法
障がい者手帳は、障がいの程度を証明するためのもので、医師の診断書をもとに申請します。
- かかりつけの病院で診断書をもらう
- 住んでいる自治体(市区町村)の窓口で申請する
- 診断結果をもとに審査が行われ、認定されると交付される
ポイント:申請から交付までに1~2か月かかることがあります。
受給者証と障がい者手帳の使い方の違い
次に、それぞれの使い道を見ていきましょう。
受給者証の使い方
受給者証は、主に福祉サービスを受けるために使います。
- 就労継続支援B型や生活介護、居宅介護などのサービス利用時に必要
- 施設の職員に提示することで、正式にサービスを受けられる
- サービス内容によって、自治体の負担額が変わる
ポイント:受給者証がないと、就労継続支援B型などの福祉サービスを受けられません。
障がい者手帳の使い方
障がい者手帳は、障がいがあることを証明し、さまざまな割引を受けるために使います。
- 公共交通機関の割引(バス・電車の運賃割引など)
- 税金の控除や減免(自動車税の減免など)
- 映画館やテーマパークの割引
- 携帯電話料金の割引
ポイント:自治体や事業者ごとに割引内容が異なるため、確認が必要です。
受給者証と障がい者手帳、どちらが必要?
「どちらを持っていればいいの?」と悩む方もいるかもしれませんが、目的が違うので、両方取得するのがおすすめです。
- 福祉サービスを利用したいなら受給者証が必要
- 日常生活での割引や支援を受けたいなら障がい者手帳が便利
たとえば、就労継続支援B型を利用したい方は、受給者証がないと利用できません。一方で、電車の運賃割引を受けたい場合は障がい者手帳が必要になります。
まとめ
受給者証と障がい者手帳の違いについてお伝えしました。
- 受給者証は福祉サービスを利用するためのもの
- 障がい者手帳は障がいがあることを証明し、各種割引を受けるためのもの
- 目的が異なるため、両方取得するとより便利に
「どっちを取得すればいいのか迷う…」「申請方法がわからない…」という方は、就労継続支援B型スマイルラボの支援員に相談してみるのも一つの手!きっと親身にサポートしてくれますよ。


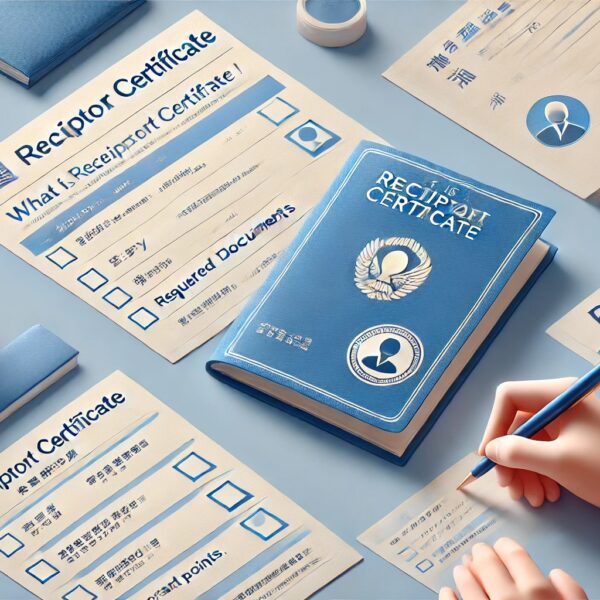










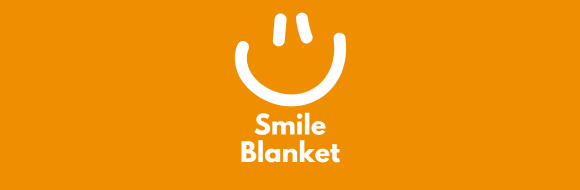
コメント