2025年4月、障害福祉の現場にとって大きな変化が訪れます。
厚生労働省は、特定技能制度の運用方針の変更を正式に決定し、居宅介護や重度訪問介護などの訪問系サービスにおいて、外国人の特定技能人材が従事できる道を開きました。
ニュース記事:https://fukushishimbun.com/series06/39532
これまでも介護分野では、技能実習や特定技能を通じて外国人が働く機会が増えてきましたが、障害福祉分野では訪問系サービスに限っては慎重な姿勢が続いていました。それだけに、「いよいよか」という空気とともに、現場では歓迎と戸惑いの声が交錯しています。
では、なぜいまこのタイミングで、訪問系の障害福祉にまで門戸が開かれたのでしょうか。その背景には、深刻な人材不足があります。訪問系サービスは、利用者の自宅に赴き、日常生活の支援を行うため、介護や生活援助とは違った専門性と責任が求められます。体力面・精神面ともにハードな仕事でありながら、担い手が足りていないという現実があります。
とくに、重度訪問介護や行動援護など、特定の障害特性に応じた個別支援を必要とするサービスは、都市部ですら人材確保が難しい状況にあります。そうした中で、これまで介護現場で成果をあげてきた特定技能の外国人材を、新たな選択肢として検討することは、必然的な流れとも言えるでしょう。
ただし、単なる“数合わせ”ではありません。今回の制度改正では、一定の研修を修了し、原則として1年以上の実務経験があること(厚生労働者)が前提とされており、誰でもすぐに訪問支援に入れるわけではありません。また、サービスを提供する前に、利用者やその家族に対して事前説明を行うことも求められています。つまり、受け入れ側の合意と信頼がなければ、配置はできない仕組みになっているのです。
加えて、厚労省だけでなく、こども家庭庁もこの方針を同時に報告しており、児童発達支援や居宅訪問型のサービスに関しても、今後は外国人スタッフが関わる場面が増えていく可能性があります。これは、単に労働力の問題にとどまらず、障害福祉の支援体系そのものを、より柔軟かつ多文化的に再編成する試みとしても捉えられます。
もちろん、制度ができたからといって、すべての現場にすぐにフィットするわけではありません。実際、視覚障がい者団体やろうあ連盟からは、「触手話など特殊なコミュニケーションが必要な現場に、すぐに外国人スタッフが適応できるのか?」といった指摘も出ています。
その一方で、「文化や言葉の違いがあるからこそ、丁寧に、心を込めて接してくれる」という前向きな評価も一部で聞かれ始めています。現段階では、まさに制度が動き始めた“入口”ですが、この一歩は、今後の障害福祉の現場に新たな風を呼び込むきっかけになるかもしれません。
次章では、現場から聞こえてくる「支援の質」への不安の声に、もう少し踏み込んで耳を傾けてみましょう。
外国人スタッフに対する不安——支援の質は本当に大丈夫?
制度が動き出すとはいえ、現場ではやはり「支援の質は本当に保てるのか?」という不安の声が根強くあります。これは利用者や家族にとってだけでなく、福祉事業所の管理者や支援員にとっても、非常に切実な問いです。
福祉支援という仕事は、単に手順通りに動けばよいというものではありません。相手の目線に立って、言葉にならない気持ちを読み取り、困っていることに自然に気づく――そんな「対人援助の感覚」が求められます。そしてそれは、日本社会の中で育まれてきた“察する文化”とも密接に関係しています。
たとえば、視覚障がいのある利用者と接する場面を想像してみてください。
言葉で説明する必要があるだけでなく、こちらが何をしているのか、今から何をしようとしているのかを、相手の不安を和らげる形で伝えるスキルが必要になります。また、盲ろうの方との支援には、「触手話」や「点字タイプライター」など、特殊なコミュニケーション技法が求められることもあり、誰もが簡単に対応できるわけではありません。
こうした場面に、文化も言語も異なるスタッフが入ったとき、本当に同じ水準の支援ができるのか?
この不安は極めて現実的です。だからこそ、日本視覚障害者団体連合や全日本ろうあ連盟などからは、「訪問系支援に外国人スタッフが入ることに強い懸念を持っている」という声が、制度検討の段階から寄せられていました。
また、事業所側としても、「通訳をつければ良い」「指差しで伝えれば大丈夫」という単純な対応では済まされない場面が多くあります。実際の支援は、一対一の密接なやりとりの積み重ね。利用者との信頼関係が非常に重要で、ちょっとした言葉の選び方や間の取り方が、安心感を生むこともあれば、逆に不信を招くこともあるのです。
さらに、現場の日本人スタッフの中には、「自分たちが一から教えることになるのでは」といった負担感を抱いている人もいます。研修はあるとはいえ、障がい特性への対応や精神面の理解は、実際に支援を通じて学んでいく部分も大きく、そこには時間もエネルギーも必要です。
とはいえ、このような不安の中にも、私たちはもう一つの視点を持っておく必要があります。
それは、「不安があるからこそ、どう乗り越えるかを共に考える機会になる」ということです。
外国人スタッフに対する不安は、言い換えれば「支援の質を大切にしている」からこそ生まれるものです。裏を返せば、それだけ日本の福祉現場が利用者一人ひとりに真摯に向き合ってきた証でもあります。そして、それは外国人スタッフにとっても学ぶべき大きな価値となるはずです。
不安はゼロにはなりません。でも、不安があるからこそ、制度や現場での準備、説明、受け入れの体制づくりが重要になってくるのです。次章では、制度がどのようにその「不安」に向き合おうとしているのか、その中身を詳しく見ていきましょう。
制度が守る“安心材料”——研修・経験・説明義務の仕組み
「本当に任せても大丈夫なのか?」
この問いに対して、制度側も決して無策ではありません。
今回、特定技能の外国人が訪問系障害福祉サービスに従事するためには、いくつかの厳格な条件が設けられています。これは、単に“人手不足を補う”というレベルではなく、質の担保を大前提とした受け入れ体制であることを示しています。
まず最も大きなポイントは、研修課程の修了と実務経験の要件です。
具体的には、日本人と同様の障害福祉サービスに従事するための研修カリキュラムを修了し、さらに原則として1年以上の実務経験を積んでいることが必要とされています。つまり、「未経験でいきなり利用者の家に訪問する」というようなことはありません。これは、最低限の知識・技術・倫理観を身につけた人材のみが従事できることを意味しています。
また、外国人スタッフが訪問系サービスに入る前には、利用者本人とその家族への事前説明が義務付けられています。これは非常に大切なポイントです。誰が来るのか、どういう経歴なのか、言語はどこまで対応できるのか――そういった情報をあらかじめ共有し、理解と納得を得た上で配置される仕組みが整っているのです。
このプロセスは、「透明性」と「合意形成」の観点から見ても重要です。
特に訪問系サービスは、プライベートな空間に支援者が入るという性質上、利用者側の安心感がなければ支援そのものが成立しません。だからこそ、この制度では“勝手に配置する”のではなく、本人の意思確認を丁寧に行うことが大前提となっています。
さらに注目すべきは、今回の制度改正が一方的な厚労省の判断ではなく、障害者部会・こども家庭審議会といった有識者の協議を経て進められたという点です。現場の声、当事者団体の意見、多様な立場からの懸念を吸い上げつつ、あくまで「実効性のある制度」として整備されてきた背景があります。
また、これらの要件は、実際の「働く場」つまり福祉事業所に対しても一定の責任を課します。外国人スタッフに対しては、適切な指導体制やフォローアップの体制づくりが必須となります。受け入れる側の覚悟と準備が求められるのです。
これを裏返せば、しっかりと制度を理解し、手順を踏んで受け入れた事業所であれば、外国人スタッフが現場で混乱を招いたり、質の低下を引き起こす可能性は極めて低いということも言えます。むしろ、制度に則ったプロセスを通して選ばれたスタッフであれば、多文化の感性や丁寧な関わり方といった新たな価値を現場にもたらす可能性すらあるのです。
制度は完璧ではありませんし、現場の工夫が求められる場面も多々あるでしょう。けれども、すでに一定の安全網は敷かれており、「心配だから導入に反対」ではなく、「どのようにしてうまく機能させるか」を考えるフェーズに入っているとも言えるでしょう。
期待される新しい支援のかたち——外国人スタッフの現場での力
「外国人スタッフ」と聞いて、最初は身構えてしまったけれど、実際に関わってみたら、その誠実さに驚かされた――。
これは、介護や福祉の現場で外国人材と働く日本人スタッフや、支援を受ける利用者から、少しずつ聞こえてくる“実際の声”です。
訪問系の障害福祉サービスに特定技能外国人が参入できるようになることで、多くの不安があるのは事実です。しかし同時に、彼ら・彼女らが現場にもたらす「新しい風」や「支援のかたち」も、確実に存在しています。
まず注目されているのが、“やさしい日本語”を用いた丁寧なコミュニケーションです。日本語を母語としない支援者にとって、複雑な表現は理解のハードルとなりますが、その代わりに、簡潔でわかりやすい言葉を使って、ていねいにゆっくりと説明しようとする努力が見られます。
この「伝えようとする姿勢」そのものが、利用者の安心感につながり、「心地よい支援」になっているという事例もあります。
また、文化的背景の違いが、時に支援に新しい視点を与えることもあります。たとえば、外国人スタッフの中には、家族的な関わりを大切にする文化を持っている方も多く、利用者に対して自然なスキンシップや親しみを込めた声かけを行うことがあります。それが「懐かしさ」や「温かさ」を感じさせるという評価もあり、言葉以上のやりとりが生まれる瞬間もあります。
さらに、外国人スタッフが現場で働く姿は、日本人スタッフにも良い影響を与えることがあります。
「言葉が完全ではないからこそ、互いに工夫して伝え合おうとする」姿勢が、チームのコミュニケーションを見直すきっかけになったり、指導者としての自覚を促すこともあるのです。
もちろん、すべてがうまくいくわけではありません。文化の違いによる価値観のズレや、慣習の違いに戸惑う場面もあるでしょう。例えば、「時間の感覚」「報連相(報告・連絡・相談)のスタイル」「謝罪のしかた」など、細かな違いが積み重なると、時には誤解が生じることもあります。
ですが、それもまた「お互いに学び合う機会」になります。
支援というのは、単にサービスを“与える側”と“受ける側”の関係ではなく、共に時間を過ごし、支え合い、成長する関係でもあります。多様な人材が現場に入ることで、支援のかたち自体が少しずつ変化していく――これは、福祉の世界にとって決してマイナスではなく、むしろ可能性だと捉えることができるのではないでしょうか。
実際に、外国人スタッフと数か月関わってみたという利用者のご家族からは、こんな声もありました。
「最初はとても心配で、正直なところ“交代してほしいかも”と思っていました。でも、毎回笑顔で来てくれて、子どもの小さな変化にもちゃんと気づいてくれて……。今では、担当がその人でよかったと思っています」
このような現場のエピソードは、単に制度上の数字や条件を超えて、人と人とのつながりの中で育まれる“支援の実感”を示しています。
不安はなくならないけれど、それ以上に「やってみたら意外といい」という声が増えていくなら、それは福祉の世界が新しいステージへと踏み出した証拠なのかもしれません。
「支援の質」を守り育てるために——今、現場ができること
制度が変わり、外国人スタッフが訪問系の障害福祉サービスに従事できるようになった今、私たち福祉の現場が向き合わなければならないのは、「どうすれば支援の質を守りながら、多様な人材とともに働いていけるか」という問いです。
これまで、日本の障害福祉は“きめ細かさ”や“思いやり”といった部分で高く評価されてきました。その背景には、支援者一人ひとりの努力と、現場で積み上げられてきた信頼の歴史があります。そこに外国人スタッフが加わることで、不安を感じるのは自然なことです。ですが、それを“排除”ではなく“調整”や“共創”という視点で捉えることが、これからの時代の福祉には求められています。
まず必要なのは、現場全体で外国人スタッフを支える意識の共有です。
「教える」「教えられる」という一方通行ではなく、「ともに学ぶ」「ともに試行錯誤する」というチームのあり方を育てていくことが大切です。そのためには、言語や文化の違いを“理解すべきハードル”と見るのではなく、“共有できる強み”として捉える姿勢が不可欠です。
たとえば、外国人スタッフの言語的な弱さを補うために、「やさしい日本語」でのマニュアルを整備したり、ピクトグラムを活用したツールを導入することで、むしろ誰にとってもわかりやすい環境が整うという副産物も生まれます。これは、高齢の利用者や軽度の認知症がある方にも役立つ工夫であり、**“伝える努力”が支援の質全体を底上げする”**という好循環にもつながります。
また、外国人スタッフにとって、最初の壁は「日本的な報連相(報告・連絡・相談)」の習慣にあるかもしれません。日本人スタッフであれば自然とできるような声かけも、文化が違えば「どこまで言っていいのか」「これは失礼にならないか」と迷うこともあります。だからこそ、現場には**“聞きやすさ”“相談しやすさ”を意識した関係づくり**が求められます。
その上で、制度側だけに任せるのではなく、事業所ごとに受け入れ体制の整備やフォローアップの工夫を持つことも不可欠です。定期的な振り返りミーティング、ペア支援の導入、日本人スタッフによるサポート体制の明確化など、小さな積み重ねが、大きな安心につながります。
利用者や家族に対しても、事前の説明やオリエンテーションの場を丁寧に設けることで、「どういう人が担当になるのか」「どんな支援スタイルなのか」を共有し、不安を最小限に抑えることができます。
私たちが目指すべきは、“日本人スタッフができる支援を、外国人にも同じようにやらせる”ことではありません。むしろ、“外国人スタッフの良さを活かしつつ、全体としてより良い支援を形にしていく”こと。そのためには、柔軟な発想と、失敗を恐れず挑戦してみる勇気が大切です。
福祉の現場は、人と人とが出会い、共に生きることを支える場所です。そこに国籍や文化の違いが加わったとしても、「良い支援をしたい」という思いさえあれば、乗り越えられる壁は多いと、私は信じています。
制度が動き始めた今、次に動くのは現場の私たち自身です。
支援の質を守るのは、誰か一人の責任ではなく、チーム全体、そして地域全体の力なのです。
まとめ
特定技能の外国人が、訪問系の障害福祉サービスに従事できるようになる。
この制度の変化は、多くの期待と同時に、少なくない不安も呼び起こしています。
「本当に大丈夫なのか?」「支援の質は守られるのか?」――。
そうした声が上がるのは、福祉の現場にいる人たちが、どれだけ“丁寧な支援”にこだわってきたかの証でもあります。
けれども、この制度は決して無防備なものではありません。研修課程の修了、実務経験、事前説明義務など、利用者と支援者双方の安心を守るための要件がしっかりと組み込まれています。そして現場では、少しずつですが、実際に働く外国人スタッフの温かさや誠実さが伝わり、「最初は不安だったけれど、今では良かったと思える」という声も生まれつつあります。
大切なのは、不安を抱えながらも、“どうすればうまくやっていけるか”を共に考えることです。支援の質は、一人で守るものではありません。支援に関わるすべての人が、対話し、補い合い、成長していくことで、よりよい支援が生まれていくのです。
変化のときには、誰しも迷います。でもその一歩が、未来の可能性を広げる扉になるかもしれません。
この記事が、その一歩を踏み出すための“小さな地図”となれたなら、執筆者としてこんなに嬉しいことはありません。





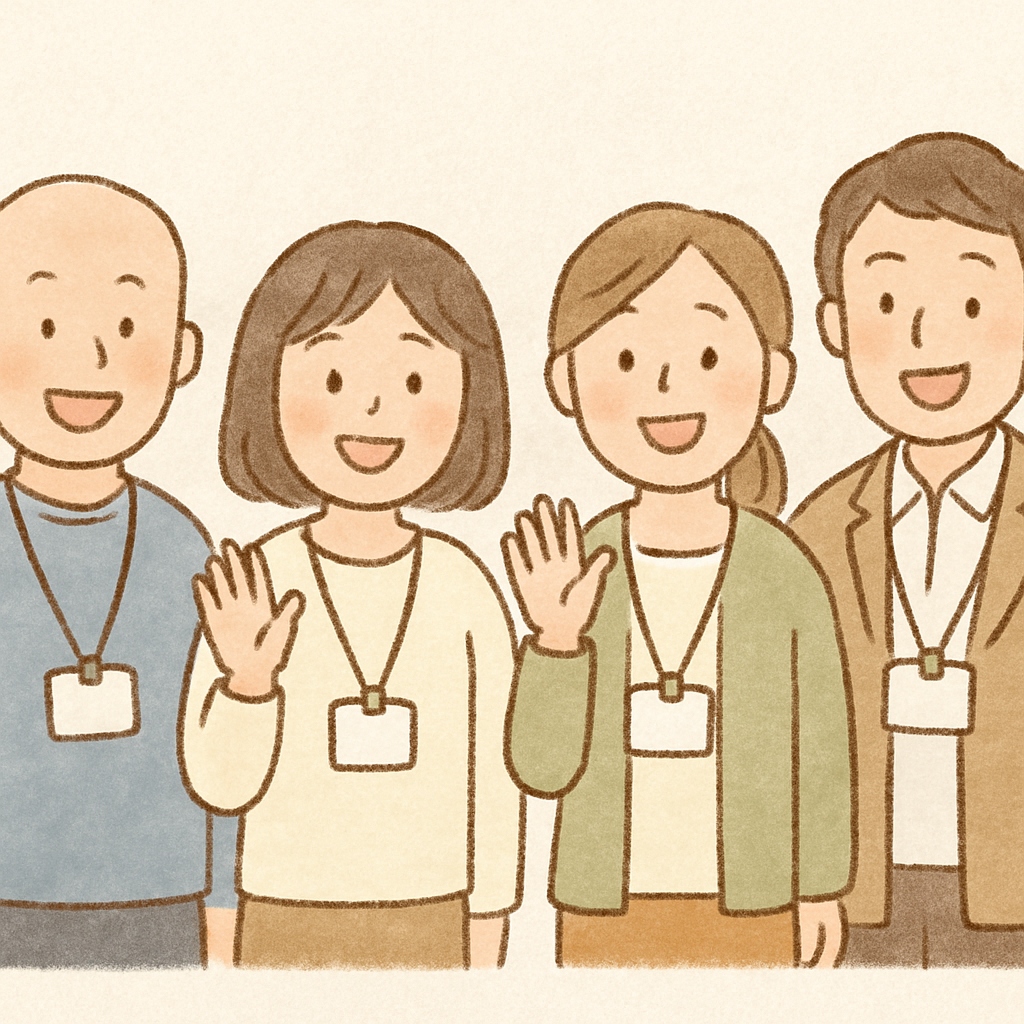

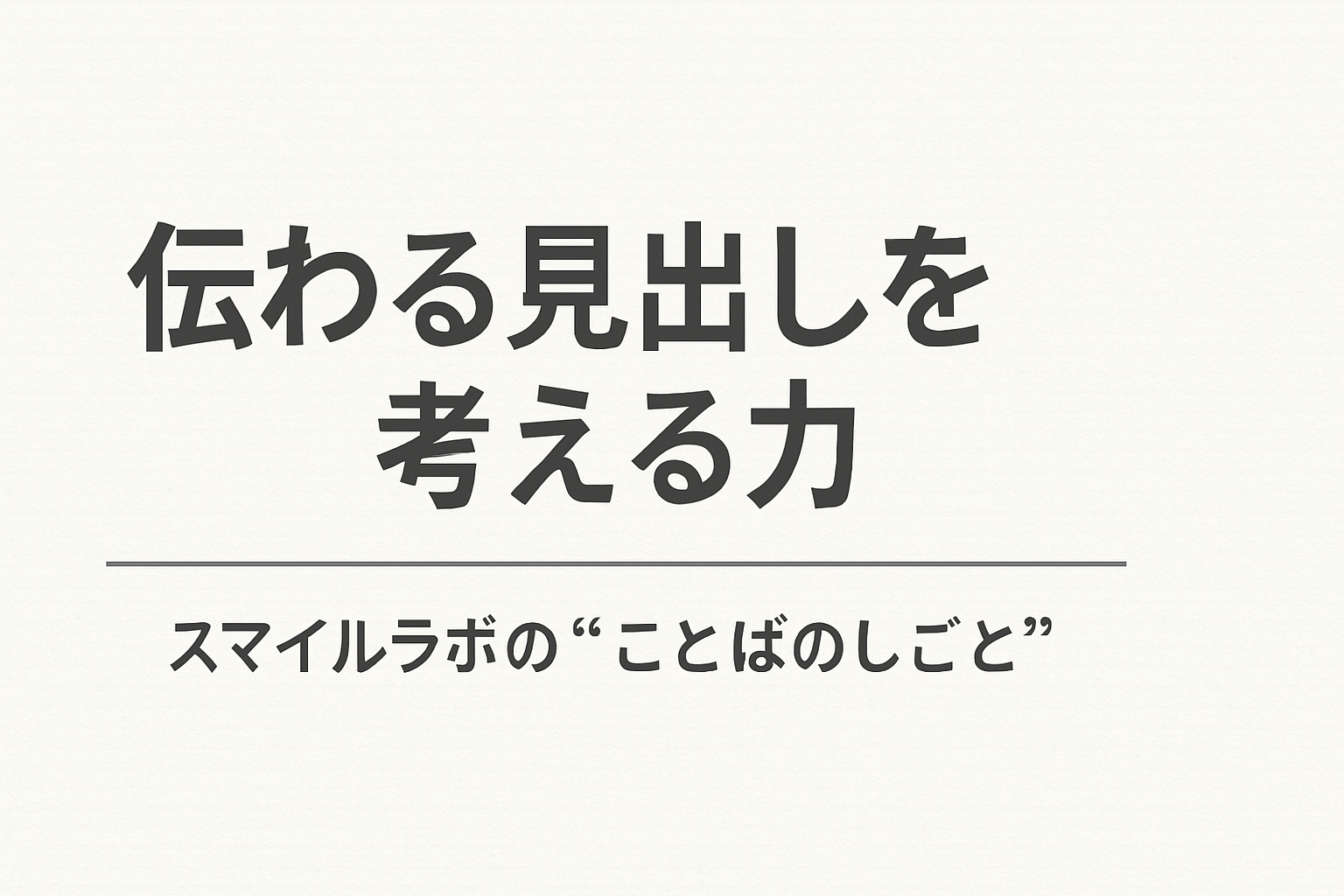
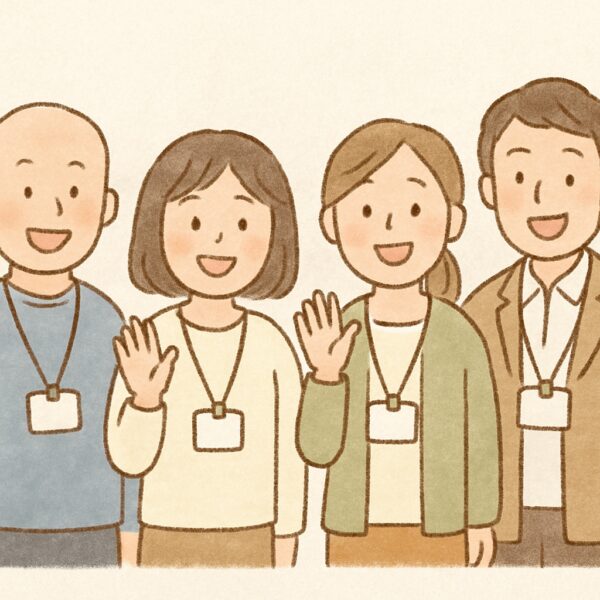

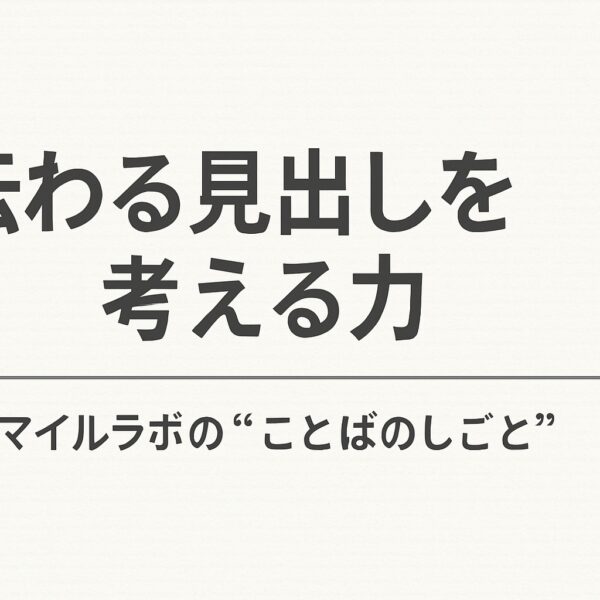




コメント