就労継続支援B型事業所で、最近こんな悩みはありませんか?
「高齢の利用者が増えてきたが、これまでのような作業が難しくなってきた」「支援員の負担も増えて、生産活動がうまく回らない」——。
利用者の高齢化や重度化は、今やどの事業所にも共通する課題となっています。しかし、その背景には、「高齢だからできない」という誤解や、支援の工夫が追いつかない現場の現実も潜んでいます。
本記事では、全国の事業所を対象とした最新の調査研究をもとに、高齢・重度化した利用者にどう対応し、生産活動を維持・活性化させていくかを具体的に解説します。
読み終えた頃には、「年齢に関係なく、その人らしく働ける場のつくり方」が見えてくるはずです。
「今すぐすべてを変えなくてもいい」。まずは、できることから一歩ずつ始めてみませんか?
利用者の高齢化・重度化が進む現場で何が起きているのか
就労継続支援B型事業所の現場では、ここ数年、利用者の年齢層が明確に上昇してきています。厚生労働省の令和6年3月の調査によれば、B型事業所の利用者のうち40歳以上は55.7%と過半数を超えており、現場では「以前よりも作業ペースが落ちている」「集中力が続かず、こまめな休憩が必要な利用者が増えている」といった変化を肌で感じている職員も多いのではないでしょうか。
また、「高齢化」だけではなく、「重度化」も同時に進行していることが重要なポイントです。精神的な不安定さや身体的な不調を抱える利用者も少なくなく、従来の支援方法や作業内容では対応しきれない場面が目立つようになってきました。
これに伴い、支援者側の負担も急増しています。たとえば、調査では「職員が生産活動に従事したり、検品を担う割合が増えた」と回答した事業所が5割を超え、事実上、職員が作業現場の一部を肩代わりしている実態が浮かび上がっています。さらに、「一部の利用者に難しい作業が集中している」「生産性が落ちた利用者が増えている」「個別支援の対応が必要な利用者が増えている」といった声も多く寄せられ、職員の時間的・精神的な負荷は深刻さを増しています。
一見すると、こうした状況は「高齢だから仕方がない」「重度化したらもう難しい」と捉えてしまいがちです。しかし本当にそうでしょうか?
調査からは、そうした諦めに傾く前に見直すべき“構造的な課題”も浮かび上がっています。たとえば、作業が画一的で柔軟性に欠けていたり、アセスメントが形骸化していたりすると、利用者の変化に気づけないまま、結果として「できる人にばかり仕事が集中する」という不公平な環境が生まれてしまいます。
また、利用者の“年齢”を表層的に捉え、加齢=戦力ダウンと判断してしまう視点そのものが支援の妨げになることもあります。実際のところ、「60代でも工程を工夫すればしっかり戦力になる」「難しい作業はできなくても、皆が気持ちよく働けるような周辺作業を担ってくれて助かっている」と語る事業所も多く、年齢だけでは語れない「役割の多様性」が現場には確かに存在しています。
このように、利用者の高齢化・重度化は避けられない現実であると同時に、支援の質が問われる重要な転機とも言えます。ただ「仕方ない」と目を伏せるのではなく、「今の支援体制で、この人に合った支援ができているか?」を問い直すこと。そこにこそ、これからの就労継続支援における希望の入口があります。
「高齢だから働けない」は誤解?本質は“個別性”
利用者の高齢化が進むなかで、支援現場ではついこんな言葉がこぼれがちです——「もう歳だからね」「若い頃のようには働けないし」。確かに、加齢によって体力の低下や持病のリスクが高まることは否めません。しかし、「高齢だから働けない」という決めつけは、支援の質を損なう大きな誤解につながります。
今回の調査研究では、多くの事業所が「年齢よりもその人の特性や希望に目を向けることが大切」との視点を持っており、「高齢=非戦力」とは一線を画す支援を実践していました。たとえばある事業所では、70代の利用者が「検品の最終確認」という重要なポジションで活躍しており、「集中力と慎重さでは若いメンバー以上」と評価されています。
重要なのは、年齢ではなく個別性。つまり、支援を考える出発点は「何歳か」ではなく、「何ができるか」「どんな作業が得意か」「どのくらいのペースで動けるか」というその人自身の特性なのです。
ところが、実際の現場では忙しさや慣れから「この作業は全員でやる」「これが決まった工程」といった画一的な対応になりがちです。これでは、軽作業でもスピードについていけない人や、逆に簡単すぎて退屈してしまう人など、さまざまな不適応が生じます。そしてそれが、モチベーションの低下や離所のリスクを高める要因にもなりかねません。
このようなミスマッチを防ぐには、個別アセスメントの質の向上が不可欠です。アセスメントとは、利用者の能力や希望を把握し、最適な支援を組み立てるための基盤。その精度が高ければ、同じ「雑貨製造」という作業の中でも「包装」「材料のカット」「在庫の管理」といった複数の役割に分けて、利用者一人ひとりに合わせたマッチングが可能になります。
また、こうした“柔軟な仕事の割り振り”は、支援者の負担軽減にもつながります。特定の人に負荷が偏らず、それぞれが無理なく貢献できる体制が整えば、支援者が作業を肩代わりする機会も減っていくでしょう。
調査に協力した事業所のなかには、「高齢の利用者こそ、ルーティンを守りながら黙々と作業できる安定した存在」として、新人の模範役としての立場を任せている例もありました。これは“高齢だから何も任せられない”という先入観を覆す、非常に示唆に富む実践です。
支援の場において、「この人は何ができるのか?」「その強みをどう活かせるか?」を丁寧に考え抜く姿勢は、年齢に関係なくすべての利用者に必要なまなざしです。年齢を理由に働く力を判断するのではなく、「その人の力が発揮される働き方は何か」を探る。この視点こそが、支援の原点であり、生産活動を支える最も確かな道筋なのです。
工夫して乗り越える!全国の事業所が実践する対応策
利用者の高齢化・重度化という現実に直面しながらも、多くの事業所は「できることはまだある」と信じ、創意工夫を重ねています。今回の調査では、全国の事業所における具体的な取り組みが多数紹介されており、その実践から私たちが学べることは非常に多くあります。
まず、多くの事業所が力を入れているのが工程の細分化です。従来は一人で「作る・詰める・梱包する」など一連の工程を担っていた作業でも、それを分解して「準備」「作業」「仕上げ」に切り分けることで、さまざまな利用者がそれぞれの特性に合った役割を持つことが可能になります。
たとえば、ある事業所では雑貨の組み立て作業を「部品の仕分け」「本体の組み立て」「完成品の検品」「梱包」と段階的に区切り、手先の器用さや集中力の持続時間などを考慮して割り振るようにしました。その結果、作業効率が向上しただけでなく、利用者自身の「自分も貢献できている」という自信にもつながったのです。
次に注目したいのが、関係機関との連携を活用した支援体制の構築です。高齢や重度の利用者にとっては、就労の現場以外の支援も欠かせません。ある地域では、事業所内に生活介護の機能を併設することで、体調の変化に応じて日々の過ごし方を柔軟に調整できる体制を整えていました。また、地域の介護サービスや医療機関と日常的に連携し、通所継続や福祉サービスの併用を通じて“働き続けられる環境”を整えている事例もあります。
さらに多くの事業所が実感しているのが、「やりがい」の力です。高齢や重度であっても、「自分のしたことが役に立っている」と感じることで、生き生きと作業に取り組むことができます。これは単に軽い作業を提供するということではなく、「その人が何に価値を感じるか」に寄り添い、役割を設計するという視点が重要です。
例えば、ある事業所では、70代の利用者が、毎朝の作業前に道具の整理整頓を行うという役割を担っています。最初は「他の作業ができないから…」という消極的な理由で始まったものでしたが、本人は毎日決まった手順で作業をこなすことで、事業所全体のスムーズな業務進行に貢献していることを実感し、今では「これは私の仕事です」と誇りを持って取り組まれています。
こうした例を見ると、「生産性」や「成果」ばかりを追い求める支援から、「参加と納得感」を重視する支援へのシフトが、利用者にとっても支援者にとっても、持続可能な働く場をつくる鍵となることがわかります。
もちろん、こうした取り組みには時間も手間もかかります。一気にすべての改善を実施するのは難しいでしょう。しかし、ほんの小さな工程の見直しや、職員間での情報共有、アセスメントの再確認といった“地味だけど確かな一歩”の積み重ねこそが、未来の安定した支援力につながっていくのです。
調査では、成果を出している事業所ほど、利用者の変化に対して“危機”ではなく“チャンス”と捉えている姿勢が共通して見られました。「この状況を機に、支援体制をもっと良くしよう」「今の利用者に合った新しいやり方を見つけよう」——。そうした前向きなまなざしが、結果として経営や工賃の改善にもつながっていることが印象的でした。
すべての利用者に「働く意味」を
就労継続支援B型事業所の使命とは、単に仕事を提供することではありません。利用者一人ひとりが「働くことの意味」を見出し、自分らしく役割を果たしながら社会とつながり続ける。そのための“場”と“支援”をつくり続けることにあります。
しかし、高齢化や重度化が進む中で、この理念が揺らぎかけている現場もあります。「もうこの人には任せられる作業がない」「できる仕事が減ってきた」といった声が、支援者の心の奥底に芽生えてしまうのです。
たしかに、生産性や工賃という数字の世界だけを見れば、年齢を重ねた利用者の作業効率は若い頃に比べて低下するかもしれません。でも、それは「働く意味」が失われることと同義ではないはずです。
むしろ大切なのは、どんな人にも、役割を持って働く場があるということを信じ、それを実現できる支援のあり方を模索し続けることなのです。
たとえば、ある事業所では、日々の作業とは別に「花を活ける」「作業場の道具を並べる」「昼食前の音読を担当する」といった“小さな役割”を大切にしています。形式的には「生産活動」ではないかもしれませんが、利用者にとってはその役割こそが「私がここにいる意味」となっているのです。
このような視点で支援を捉え直すとき、支援者の側にも変化が求められます。単に作業を教え、結果を管理する立場から、利用者と共に「その人らしい働き方」を探し続ける伴走者としての姿勢が必要になります。それは一見すると効率が悪いように思えるかもしれませんが、実はこうした姿勢が長期的な定着と安定した通所、そして支援現場の持続可能性に大きく貢献するのです。
調査報告書でも、こうした姿勢を実践している事業所ほど、支援者の定着率が高く、利用者も長く安心して通っている傾向が見られました。それは単にスキルやノウハウの問題ではなく、「人を大切にする文化」が根づいていることの証しと言えるでしょう。
また、過疎地や地方の事業所では、利用者だけでなく職員も高齢化している現実があります。そうした地域では、「障害者も高齢者も一緒に、地域の中で働ける場をどうつくるか」という、より包括的な問いに向き合っている事業所も出てきました。これはまさに、福祉の枠を超えた“共生のしごと”を模索する営みと言えるでしょう。
すべての利用者にとって「働く意味」を支えるということは、一人ひとりの尊厳を支えるということ。
「できないこと」を数えるのではなく、「できること」と「やってみたいこと」を丁寧に拾い上げ、それを“役割”という形にしていく。その地道な営みこそが、就労支援の本質であり、これからの生産活動を活性化させる原動力となるのです。
まとめ:支援の質が未来をつくる——年齢や障害を超えて「働く」を支えるために
就労継続支援B型事業所において、利用者の高齢化・重度化は確実に進行しています。これまで通りの作業体制では通用しなくなり、職員の負担も増大しているなかで、「どうすれば生産活動を維持しながら、すべての利用者に“働く場”を提供し続けられるのか?」という問いに、現場は向き合い続けています。
本記事では、その課題に対して、全国の事業所がどのような工夫を重ねてきたかを紹介してきました。
-
「高齢だから無理」と決めつけず、個別の特性と希望に基づいて支援すること
-
作業工程を細分化し、負担の分散とマッチングの質を高めること
-
関係機関と連携しながら「長く働ける環境」を整えること
-
数字だけでなく、利用者自身の“やりがい”や“納得感”を大切にすること
これらのアプローチはどれも、利用者一人ひとりの「働く意味」を支えるための土台です。今後さらに多様化・高齢化が進むであろう支援現場において、求められるのは柔軟で、丁寧で、そして創造的な支援の在り方です。
たとえできることが少なくなったとしても、「誰かの役に立っている」「今日も自分にできることがある」と感じられる環境があれば、人は前向きに生きられます。支援者として、そうした日々を共につくっていく姿勢こそが、工賃や経営の改善といった結果にもつながっていくでしょう。
✅読了後にできること:
-
現場の作業工程を再点検し、工程分解の可能性を探る
-
利用者一人ひとりのアセスメントを見直し、特性に合った支援設計を再検討する
-
関係機関や地域資源との連携状況をチェックし、支援体制の補強を図る
まずは、小さな一歩から。
それが、支援の未来を変えていく確かな力になるはずです。








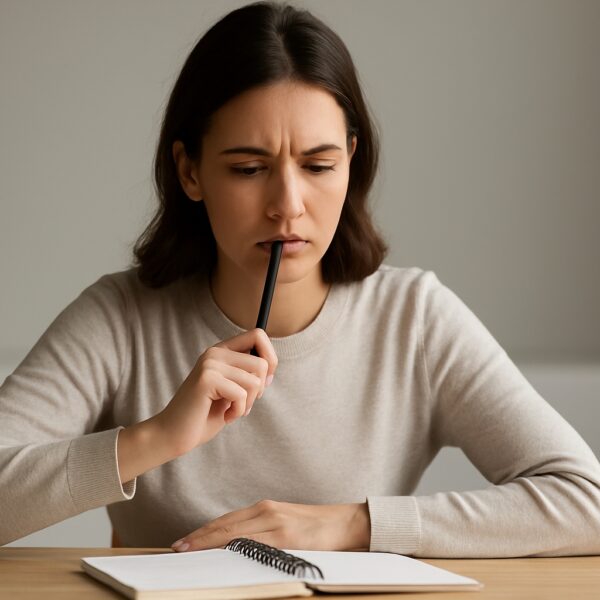



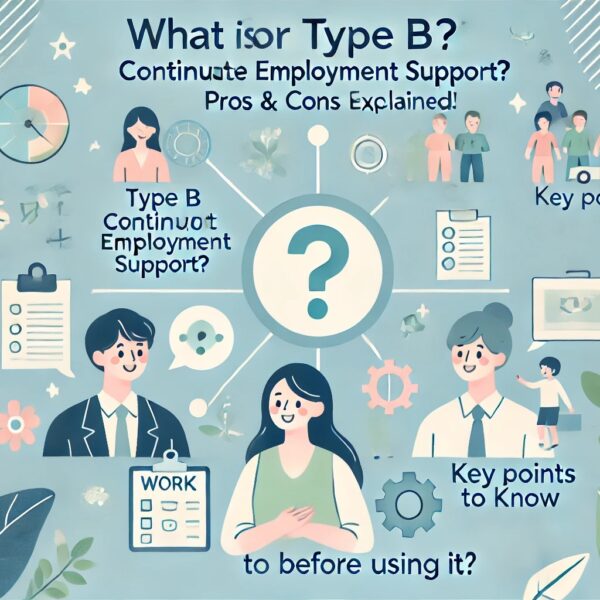
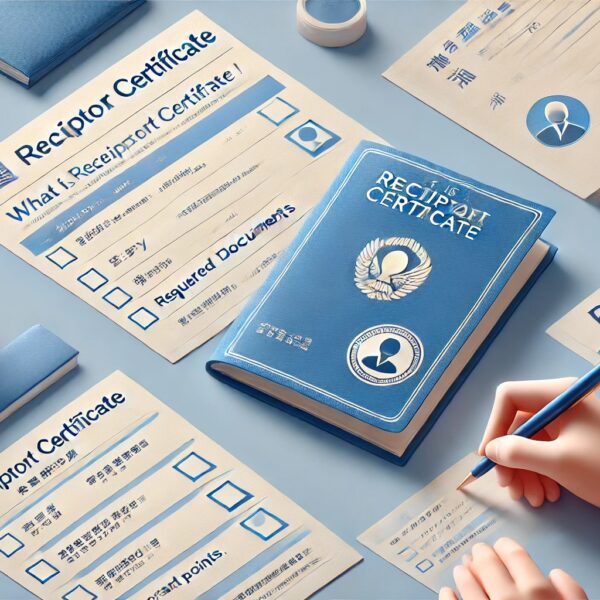


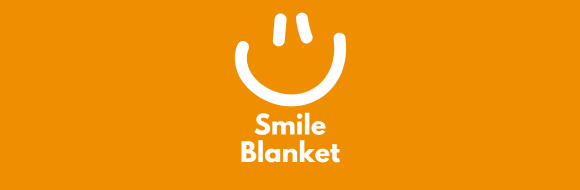
コメント