就労継続支援B型の現場では、知的障害・発達障害・精神障害など、異なる特性を持つ利用者がともに働いています。しかし支援をしていると、「この人にはどう接すればいいのか…」「同じ説明が通じない」など、思うように支援が届かない場面に直面することもあるのではないでしょうか。
本記事では、そうした「支援が通じない」と感じる背景にある“障害特性の違い”に焦点を当て、現場でできる具体的な支援の工夫や考え方をご紹介します。
なぜ支援がすれ違ってしまうのか? どんな視点を持てば支援は届くのか? それぞれの障害特性を尊重しながら、誰もが安心して働ける場をつくるヒントを、実際の事業所の事例も交えてお伝えします。
「支援の正解がわからない」——そんな戸惑いを抱えるすべての支援者にとって、小さなヒントが見つかる内容です。ぜひ最後まで読んでみてください。
支援が通じない…多様な障害特性に現場はどう対応する?
就労継続支援B型事業所では、さまざまな障害特性を持った利用者が一緒に働いています。知的障害・発達障害・精神障害——それぞれの障害には異なる認知や感覚の特徴があり、当然ながら一律の支援方法ではすべての人にうまく届きません。
たとえば、「声をかけただけなのに不安定になってしまった」「いつもと同じ説明のはずなのに、ある利用者には伝わらない」など、支援がうまくいかない場面に直面したことのある職員も多いのではないでしょうか。それは、支援者の努力不足ではなく、障害特性によって「情報の受け取り方」や「安心を感じる条件」が大きく異なるからなのです。
最近では、B型事業所に通う利用者の層が広がり、より多様化が進んでいます。かつては知的障害のある方が多数派だった時代から、現在では精神障害や発達障害のある方も多く利用されるようになってきました。その結果、同じ支援方針で全体をまとめることが難しくなり、支援者側にも「誰に合わせて支援を組み立てるべきか」が見えづらくなっているという現実があります。
また、障害のある方々は、表面上は同じように見える作業や環境でも、それぞれに感じ方や捉え方がまったく異なります。ある人にとっては「安心できるいつもの環境」が、別の人にとっては「緊張や混乱を招く要因」になってしまうこともあるのです。たとえば、大きな声で励ましたつもりがパニックを引き起こしたり、作業中に急に話しかけたことで集中が切れてしまったり──支援の“すれ違い”が生じやすい背景には、こうした特性の違いがあります。
そしてもう一つ、現場が疲弊しやすい要因として、「支援者がすべての障害特性に精通していなければいけない」という過度なプレッシャーもあります。利用者の特性を把握しながら、ひとりひとりに合った支援を常に行うことは、理想ではあるけれど現実には非常に困難です。とくに、人手不足や時間の制約がある現場では、「わかっていても対応できない」ことも多く、それが支援者の罪悪感や無力感につながるケースも見られます。
しかし、こうした“通じない支援”が起きること自体は、支援現場において自然なことであり、避けようとしても避けられるものではありません。むしろ大切なのは、支援が通じなかったときに「この人にはどんな支援が合うのだろう?」と考え直す姿勢を持つこと。そこから、ひとりひとりの特性に応じた柔軟な支援へとつなげていくことが、これからのB型支援に求められる力ではないでしょうか。
次章では、なぜこの“すれ違い”が生まれるのか、その背景となる障害特性ごとの認知の違いや誤解のリスクについて、より具体的に見ていきます。
障害特性によって支援が“すれ違う”理由
支援現場でよく聞かれる「同じように説明しているのに、なぜかうまく伝わらない」という悩み。その背景には、障害特性ごとの“情報の捉え方”や“感情の反応の仕方”の違いがあります。
つまり、支援の内容が問題なのではなく、「伝わり方」が人によってまったく異なるということです。
たとえば、発達障害のある利用者の場合、口頭での指示や抽象的な言い回しが理解しづらいことがあります。「ちょっと早めに終わらせてね」などの曖昧な表現は、「何時までに終わらせればいいのか?」と混乱を招きます。また、順序のわからない説明や、突然の予定変更に大きな不安を感じやすく、落ち着きを失うケースも少なくありません。視覚的な情報を重視し、「見える化」された手順が支援の効果を高める一因となるのはそのためです。
一方、精神障害のある利用者では、感情の変化や気分の波が日によって大きく、同じ支援でもタイミングや声のトーンによって受け取り方が変わることがあります。過去のトラウマ体験や対人不安から、支援者の善意の関わりが「干渉」「否定」として受け取られることもあります。本人のその日の調子や“距離感”を意識した関わりが重要です。
また、知的障害のある利用者は、作業や説明の一貫性が失われると混乱しやすい傾向があります。日々のルーティンを大切にし、繰り返し同じ形で支援を行うことで安心感と学習の定着につながります。「昨日と言ってることが違う」「やり方がコロコロ変わる」ことは、予想以上に不安の原因になります。説明はシンプルに、そして同じ表現で繰り返すことが大切です。
このように、同じ言葉・同じ対応が、人によってまったく違う意味に変換されてしまうというのが、支援のすれ違いの根本にある問題です。そして、これを防ぐには「正しい支援マニュアルを持つ」こと以上に、その人の特性に“寄り添いながら理解する姿勢”が求められます。
さらに、特性は「混ざって」現れることも多くあります。たとえば、知的障害と発達障害を併せ持つ利用者は、単純な「知的な理解の困難さ」だけでなく、感覚過敏やこだわりの強さも同時に抱えていることがあります。精神障害のある方でも、注意欠如や情報処理の特性が重なっていることは少なくありません。このような「グラデーション状の特性」が現場の支援を複雑にしています。
だからこそ、表面の行動だけを見て「わがまま」「非協力的」と判断するのではなく、「なぜ今そういう反応が起きたのか?」という視点を持つことが、最初の一歩です。そしてそれは、専門的な知識よりも、“この人はどんなことで不安になるのか?”という想像力から始まるものなのです。
支援における“すれ違い”は、必ずしも避けられるものではありません。しかし、それに気づいた瞬間から、支援の方向は変えられます。
次章では、実際に現場で行われている具体的な支援の工夫を紹介し、多様な障害特性にどう対応しているのかを見ていきましょう。
多様な障害特性に応える支援の工夫
「この人にはこの支援が合っていた。でも別の人にはうまくいかなかった」
——このような経験は、現場に立つ支援者なら誰しも一度は味わっているのではないでしょうか。
多様な障害特性を持つ利用者が通所するB型事業所では、一律の支援が通用しないのが日常です。
だからこそ、支援者たちは現場の中で試行錯誤を重ねながら、それぞれの人に合った支援の形を模索しています。ここでは、実際のB型事業所が実践している工夫を紹介します。
①視覚的支援と「見通し」の提示で安心感をつくる
発達障害や知的障害のある利用者に多いのが、「先のことがわからないことへの不安」です。口頭で「このあと〇〇して」と伝えるだけでは、イメージができずに混乱してしまうことがあります。
そこで有効なのが、視覚的な支援ツールの活用です。
たとえば、
-
作業手順を写真つきで貼り出す
-
ホワイトボードに「今日のスケジュール」や「やることリスト」を記載する
-
色分けされた作業トレーを使い、「これが終わったら次」と順番が自然にわかるようにする
こうした支援は、安心感を生み出すだけでなく、自立的な行動にもつながります。毎回「何したらいいですか?」と聞いていた利用者が、掲示物を見ることで自分から動けるようになったという例も少なくありません。
②作業の選択肢を用意して「自分で決める」感覚を支える
精神障害のある利用者の場合、その日の体調や気分によって作業の難易度やペースが左右されることがよくあります。そうした方に「これをやってください」と一方的に仕事を割り当てると、心理的な負荷が強くなり、結果として離席や離所につながってしまうこともあります。
その対策として多くの事業所で取り入れられているのが、作業の“選択制”です。
たとえば、
-
「今日は封入とラベル貼り、どちらにしますか?」とあらかじめ選択肢を用意する
-
一日の中で午前・午後にわけて作業の内容や負荷を選べるようにする
自分で選ぶというプロセスが、安心感や主体性につながり、結果として継続的な通所にも結びついています。支援の目的は“やらせること”ではなく、“続けられること”。この考えが、こうした取り組みの背景にあります。
③手順の一貫性と反復で「できる」を積み重ねる
知的障害のある方にとっては、作業内容の安定や手順の明確さがとても重要です。前回と手順が違ったり、支援者ごとに説明が変わったりすると、それだけで混乱を招きやすくなります。
そのため、
-
支援の際には同じ言葉を使う
-
作業前後の流れをルーチン化する(例:朝の準備→作業→記録→片付け)
-
毎日できたことをフィードバックして「できている実感」を育てる
こうした一貫性と反復の支援が、学習の定着を助け、「やればできる」という自己効力感を育てていきます。
すべてに共通するキーワードは「予測可能性」と「安心感」
これらの工夫に共通しているのは、先が読めること(予測可能性)と、無理をさせないこと(安心感)です。
利用者の障害種別はさまざまでも、「わかりやすく」「選べて」「繰り返せる」支援には共通して安心があり、それが生産活動の継続や意欲につながっていきます。
また、こうした工夫は職員の支援負担も減らすことができます。「何度言っても伝わらない」と感じていたことが、視覚支援や選択制でスムーズになり、「指示しなくても動ける」場面が増える。支援者の疲弊を防ぎ、利用者の自立を促す好循環が生まれるのです。
このように、障害特性に合わせた支援の工夫は、難しいテクニックではなく、「見やすく」「わかりやすく」「選べる」環境を整えることから始まります。
次章では、こうした工夫の根底にある「支援者のまなざし」について掘り下げていきます。
答えはひとつじゃない。だからこそ“支援力”が問われる
B型支援の現場において、もっとも困難であり、同時にもっともやりがいのあること——それは、「正解がひとつではない」世界で支援を続けていくことです。
障害特性は千差万別。同じ“発達障害”という診断名であっても、ある人には視覚支援が有効でも、別の人には逆に混乱を招くこともある。ある利用者に「この方法がよかった」と思っても、他の利用者にはまったく響かないこともあります。
この“支援の揺らぎ”に直面したとき、私たち支援者はしばしば戸惑います。「今の関わり方でよかったのか?」「あの人にはもっと違う声かけが必要だったのでは?」
そして、それに対する明確な答えはない——そこが、支援という仕事の難しさでもあり、深さでもあります。
だからこそ、支援者に求められるのは、万能な正解を求める姿勢ではなく、「目の前の人に合う支援を、いまこの場で考える力」です。そしてその力の源は、特別な資格や経験ではなく、“この人のことをもっと知りたい”というまなざしにあるのです。
現場の調査(参考資料;就労継続支援事業における生産活動の活性化に関する調査研究)でも、支援がうまく機能している事業所には、いくつかの共通点が見られました。
まずひとつは、「失敗を恐れず、試してみることを良しとする空気」があること。支援に正解がないからこそ、何度でもやり方を変えてみる、試してみる、そして利用者と一緒に「これがいいかもしれないね」と育てていく。そうした文化が、職員一人ひとりの“支援の柔軟さ”を支えています。
もうひとつは、「悩むことそのものが、前に進む力になっている」こと。支援がうまくいかないとき、それを“失敗”と捉えるのではなく、“気づき”として受け取り、次につなげる視点を持つこと。それによって、支援者は疲弊ではなく、成長のプロセスを積んでいくことができるのです。
こうした姿勢は、利用者にとっても安心につながります。支援者が「この人にはどんな関わり方が合うか?」を丁寧に考えている姿は、言葉にしなくても利用者に伝わります。そしてその“自分を尊重してくれている”という感覚は、信頼や安定した通所につながっていきます。
つまり、支援力とは「知識の量」だけで測れるものではありません。
それは、試行錯誤を続ける姿勢であり、利用者との関係のなかで育まれる力なのです。
多様な利用者が集まるB型事業所は、単なる「障害者の働く場」ではありません。そこは、多様な個性と向き合い、共に悩み、共に進んでいく、小さな“共生の現場”です。
だからこそ、正解を求めすぎなくてもいい。
大切なのは、今日、目の前の利用者とどう向き合ったか。
そして明日、その人のために何を変えてみようと思ったか。
その積み重ねこそが、現場の支援力を育て、B型支援の未来を支えていくのです。
まとめ:多様な特性にこそ応える支援を——「正解」ではなく「姿勢」が現場を支える
就労継続支援B型の現場では、知的障害・発達障害・精神障害など、多様な障害特性を持つ利用者が日々ともに働いています。
この「多様性」は時に支援の複雑さやすれ違いを生み、支援者を迷わせ、悩ませる要因にもなります。
しかし、そうした悩みや葛藤のなかにこそ、支援の本質があります。
一律ではない支援が求められるからこそ、「この人には、どう関わるのがよいのか?」という問いが生まれ、支援者としての成長が促されていくのです。
本記事では、障害特性ごとの違いや、その特性に対応した具体的な支援の工夫、そして“正解がない支援”に立ち向かう姿勢の重要性についてご紹介しました。
「伝わらない」「通じない」と感じたとき、それは支援の終わりではなく、“より良い支援の始まり”です。
✅読了後にできる、明日からの一歩
-
利用者一人ひとりの“受け取り方の違い”に改めて目を向けてみる
-
支援がうまくいかなかった場面を振り返り、「なぜそうなったのか?」を考えてみる
-
「もっと合う支援は何だろう?」というチームでの共有と対話を大切にする
特別な支援方法でなくてもいいのです。
「この人のために、支援を少し変えてみよう」という気づきと実行こそが、B型事業所の“支援力”を形づくっていきます。
支援に迷うこと、それ自体が力になる——
そんなまなざしを大切に、これからも一緒に現場を支えていきましょう。


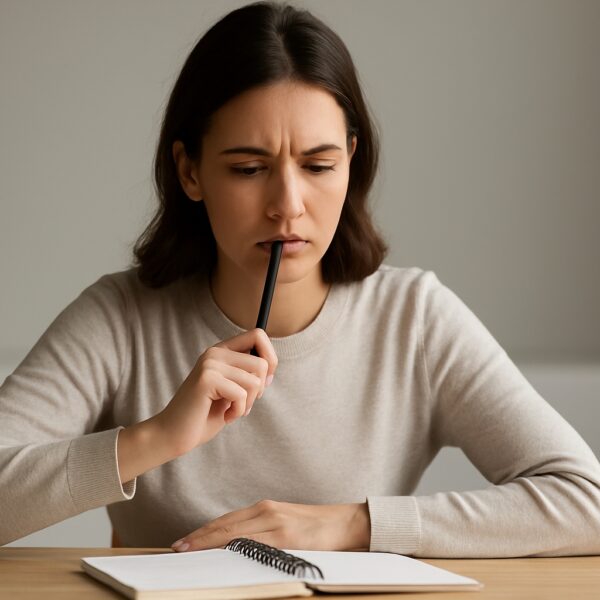







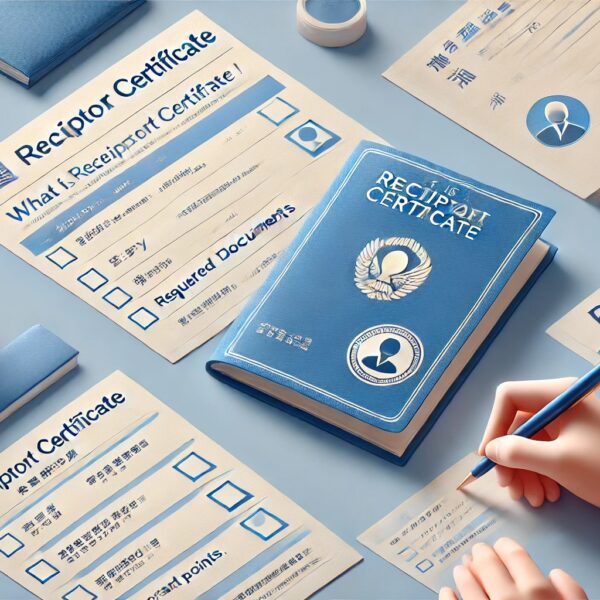
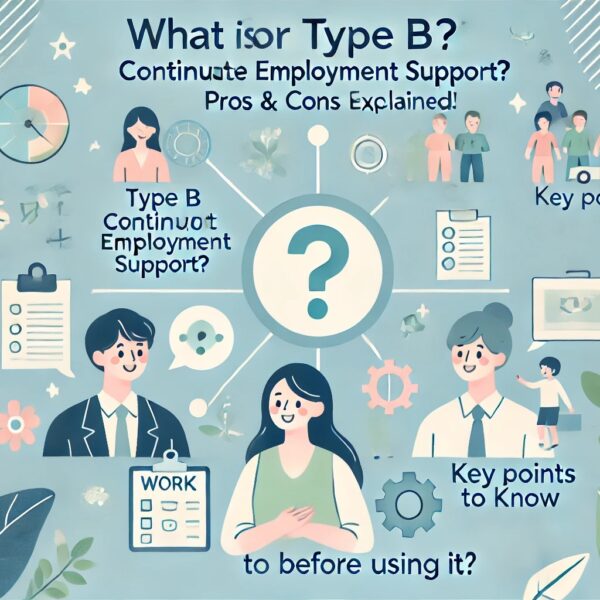



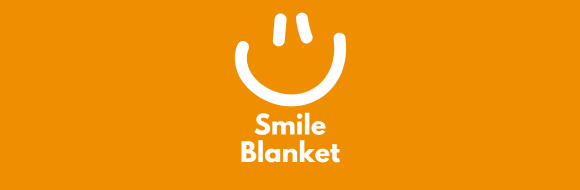
コメント