「補助金?うちには関係ないと思ってました」
そんな声を、福祉の現場でよく聞きます。ですが、申請さえすれば受け取れたはずの補助金を、情報不足で逃してしまっている事業所は決して少なくありません。この記事では、障害福祉事業所が活用できる補助金制度の中でも、特に就労継続支援B型の現場で見落とされがちな「障害福祉人材確保・職場環境改善等事業補助金」を中心に、誰が・どこに・いつ・どう申請するべきかを、やさしく整理してご紹介します。「読むだけで数万円得するかもしれない」内容です。
まずは自分の事業所が対象かどうか、一緒に確認してみませんか?
気づかぬうちに補助金を逃しているかもしれない
「あれ?それってうちももらえたんですか?」
これは実際に、現場でよく聞かれる言葉です。就労継続支援B型などの福祉事業所を運営していると、日々の支援業務や記録、請求業務、ミーティングと、目の前の業務に忙殺されがちです。その中で、「補助金制度の案内が来ていたけど、読まずにスルーしてしまった」「うちには関係ないと思って申請しなかった」という方も少なくないのではないでしょうか。ですが、その思い込みが、実は数万円〜数十万円の機会損失につながっていたら…?
補助金制度は、いわば“手を挙げた人にだけ届く支援”です。制度の存在を知っていても、提出先が分からなかった、提出期限が過ぎていた、そもそも自分が対象なのか分からなかった…。その結果、活用できたはずの補助金を取り逃してしまったケースは少なくありません。特に「障害福祉人材確保・職場環境改善等事業補助金」のように、年度ごとの予算枠で動いているものは、一度逃すと基本的に次年度まで待たなければならないのが現実です。
「うちは小さいから」「まだ新規指定されたばかりだから」そう思って見過ごしてしまう前に、まずは制度の存在を知り、自分の事業所が対象かどうかをチェックすること。実はそこからすでに補助金活用は始まっているのです。
🟪申請しなければもらえない制度の落とし穴
補助金制度の多くは、申請があって初めて成立します。つまり、対象であっても、申請しなければ一切支給されません。たとえば「職場環境改善等事業補助金」は、支援員の定着や就労支援の環境整備に使える便利な制度ですが、毎年春(多くは4月)に締切が設定されており、そのタイミングを逃すと、どんなにニーズがあっても翌年度まで待たなければなりません。「気づいたときには遅かった…」という声が多いのは、まさにこの申請制ゆえの落とし穴と言えるでしょう。
🟪 「うちは対象外」と思い込んでいませんか?
「新規指定だから今年は関係ないだろう」「小規模だからうちは対象じゃないはず」…そんな思い込みが、実は補助金を遠ざけています。実際には、自治体によっては途中指定の事業所にも申請枠を設けていたり、報酬実績があれば補助金額が自動的に算出されたりと、対象のハードルはそこまで高くありません。とくに人材定着や環境改善が課題になりがちな小さな事業所こそ、制度をフル活用すべき存在なのです。
補助金制度の基本と「申請先が違う」落とし穴
補助金制度を活用するには、まず「どの制度が、誰に向けられていて、どこに申請するのか」を理解することが第一歩です。中でも注意したいのは、「提出先の自治体が事業所の所在地によって異なる」という点です。これは意外と見落とされがちで、実際に「法人本部は伊丹市にあるが、事業所は尼崎市にある」という場合、申請先は尼崎市になるという具合です。
たとえば、兵庫県では三田市・赤穂市・豊岡市などの一般市に所在する事業所は、兵庫県庁に対して補助金を申請します。しかし、尼崎市のような中核市では、指定権限が市に移譲されているため、補助金の申請も尼崎市に直接提出しなければなりません。これを知らずに県に送ってしまうと、「受け付けていません」と門前払いされることもあります。
さらに、補助金によっては国レベルの予算事業(たとえば障害者総合支援事業費補助金など)であっても、実際の実施主体は都道府県や市町村というケースがほとんどです。つまり、制度を理解していても、どこに届け出ればいいのかを間違えると、その段階でスムーズに給付を受けることが難しくなってしまうこともあるのです。
だからこそ、提出前に「この補助金は、うちの事業所がある市に出すのか、県に出すのか?」と一度確認するだけで、大きなリスクを避けられます。思い込みは禁物。自治体の公式サイトや福祉課に電話一本入れることが、制度活用の第一歩になります。
🟪 県?市?就労継続支援B型の申請先とは
就労継続支援B型の補助金申請は、事業所の所在地によって提出先が変わります。一般市(例:三田市・赤穂市など)にある場合は県が窓口ですが、中核市(例:尼崎市・西宮市)は市が直接受付窓口となります。つまり、同じ兵庫県内でも申請書の行き先が異なるのです。ちなみにスマイルラボのある尼崎市では、職場環境改善等事業補助金の申請を兵庫県にするようにホームページで案内されています。(尼崎市ホームページ)
提出先を間違えると受理されず、期限内に間に合わなくなるリスクもあります。まずは、事業所の所在地と自治体の権限移譲の有無を確認することが重要です。
🟪 基準月の報酬から算出される補助金の仕組み
職場環境改善等事業補助金の額は、基準月(多くは12月)の国保連請求額に、定められた交付率を掛けて算出されます。たとえば、12月の総報酬が140万円で、交付率が5.5%と定められている場合、補助金額は77,000円となります。この金額は年に1回、まとめて交付されるのが一般的です。利用者数や加算の取得状況によっても金額が変動するため、見積もりが難しいときは自治体に確認を依頼するのも一つの方法です。
補助金は職場の未来をつくるチャンス
補助金を受け取ることは、単にお金が入るというだけではありません。それは、日頃から頑張ってくれている職員への感謝を形にしたり、環境を整えることで支援の質を高めたりする、職場づくりの転換点になるチャンスでもあります。
とくに就労継続支援B型の現場では、「職員が疲弊してしまう」「支援員がなかなか定着しない」という声をよく耳にします。人件費を補うだけの収益を確保するのが難しいこの分野において、補助金は本当に貴重な外部資源です。
たとえば、支援員一人あたり年に1〜5万円相当の補助が得られれば、そのまま年末手当や交通費の補填、福利厚生の充実などに充てることができます。また、冷暖房の整備、個別支援用の備品購入、職員研修の費用として活用することも可能です。
つまり、「どう使うか」は事業所の創意工夫に委ねられており、うまく活用すれば職員のやる気や安心感にも直結します。
さらに見逃せないのは、こうした補助金を適切に活用し、自治体への報告をしっかり行っていくことが、「信頼される事業所づくり」にもつながるという点です。きちんと制度を理解し、適切に運用している事業所には、自治体からも評価や相談が集まりやすくなり、結果的に地域との連携も深まっていくのです。
補助金を「ありがたい臨時収入」と考えるだけでなく、それをどう活かして“これからの現場”をつくるか。その視点を持てるかどうかが、これからの福祉現場の持続可能性に大きな影響を与えるのではないでしょうか。
🟪 職員に還元するだけじゃない、幅広い活用方法
補助金の活用方法は意外と幅広く、「必ず職員に現金で支給しなければならない」というものではありません。たとえば、エアコンの設置や作業机の改善などの設備投資、職員向けの研修費、業務の効率化につながるITツールの導入費用なども対象になります。つまり、職員が働きやすいと感じられる環境づくりに貢献するものであれば、形にこだわる必要はないのです。大切なのは、「このお金で何を改善したいのか」という視点を持つことです。
🟪 まずは「うちは対象か?」と確認してみよう
忙しい日常の中で、補助金の情報収集や申請手続きを後回しにしてしまう気持ちはよく分かります。でも、ほんの数分、「うちはこの補助金の対象になるのか」と確認するだけで、数万円〜十万円規模の支援につながるかもしれません。わからなければ、遠慮せずに自治体に問い合わせてみましょう。「知らなかった」「気づかなかった」で終わらせないために、まずは情報の扉を開いてみること。それが未来の支援現場への第一歩です。
✅ まとめ:見逃さない、活かしきる。その一歩が、未来を変える
補助金は、制度としてそこに“ある”だけでは意味を成しません。
それを知り、対象かどうかを調べ、手を挙げ、正しく活用してこそ、本当に事業所や職員の力になります。今回ご紹介した「障害福祉人材確保・職場環境改善等事業補助金」も、そうした制度のひとつです。
制度の複雑さに戸惑ったり、提出先が分からずに諦めてしまったりすることもあるかもしれません。でも、だからこそ「うちは対象なのか?」「どこに申請すればいいのか?」と、自分から動くことが、すべての始まりです。
大きな補助金でなくても、職場を少しだけ明るくするエアコンの設置、疲れた職員に少しでも喜んでもらえる手当、利用者とのコミュニケーションがより円滑になる備品の整備——その一つひとつが、事業所の未来をつくっていくのです。
どうか「知らなかった」で終わらせないでください。
制度は、私たち支援者を支えるためにも、用意されています。
その手を、ぜひ伸ばしてみてください。
✅ 読了後にすべきこと
-
ご自身の事業所所在地が属する自治体(市か県か)を確認
-
「障害福祉人材確保・職場環境改善等事業補助金」の募集要項・時期を確認
-
新規指定・途中指定の場合、個別に問い合わせをしてみる
-
過去の国保連請求実績を見直し、見込み金額を試算してみる
-
補助金の活用目的(何を改善したいか)をチームで話し合う




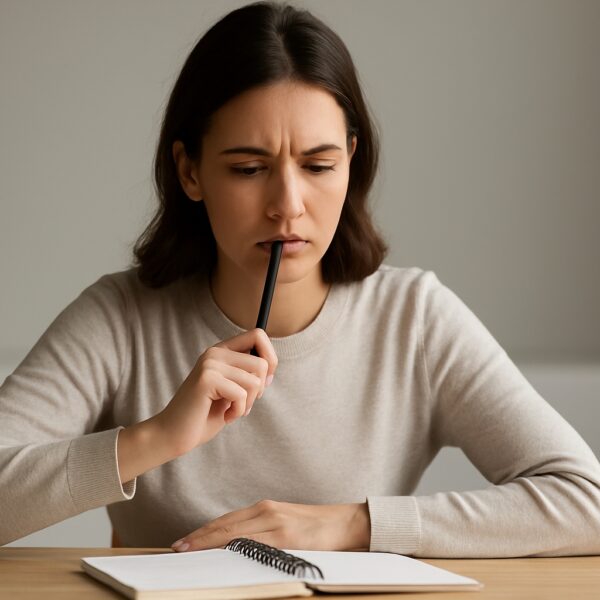


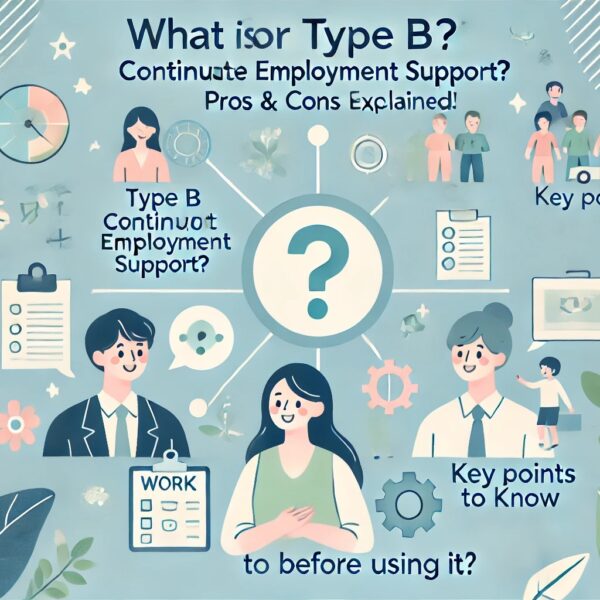



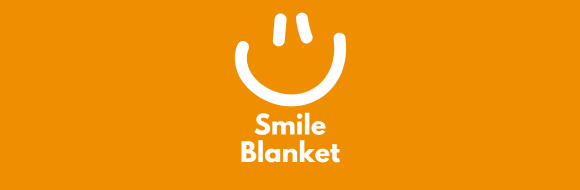
コメント